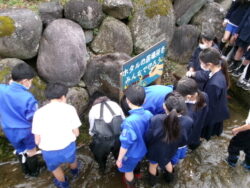4年生 宿泊学習 1日目③
宿泊学習1日目、夕方から夜にかけての様子を紹介します。
夕食後は入浴しました。マナーを守って、楽しく入浴している様子でした。
その後は、星空観察を行いました。講師の先生に解説をしてもらいながら、プラネタリウムを観賞しました。北極星や夏の大三角に関する星座の見付け方を分かりやすく教えていただき、子供たちは「おー!」と歓声をあげながら見ていました。


その後、実際の夜空を観察しました。子供たちは教えてもらったことをもとに「あれが夏の大三角形かな?」「北斗七星を見付けたよ!」と話しながら、夢中になって星空を観察していました。また、望遠鏡も見せていただき、「月にでこぼこがあったよ!」など、詳しく見た天体に驚いている様子でした。

今日一日、元気に充実した活動を行った子供たちでした。ゆっくり休んでほしいと思います。
明日はジョイフレンドや焼き板作りに挑戦する予定です。